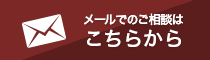- 2016/02/20
- 不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合における、再度の取得時効の完成と上記抵当権の消長
(最判平成24年3月16日民集66.5.2321)
| 事案の概要 | Aは、昭和45年3月、その所有する土地をXに売却し、Xは同月から現在(本件訴訟提起時現在(平成22年))まで同土地の占有を続けてきたが、所有権移転登記手続は行われていなかった。
Aは昭和47年に死亡し、その相続人であるBが、昭和57年1月、本件土地につき相続を原因として所有権移転登記をした上で、金融機関Yに対し、昭和59年4月に甲抵当権を、昭和61年10月に乙抵当権をそれぞれ設定し、その旨の抵当権設定登記がなされた。なお、乙抵当権の被担保債権は、平成9年に完済された。 平成18年9月、Yは、本件土地につき抵当権の実行としての競売を申し立て、競売開始決定が出た。 これに対し、Xは、「不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権移転登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗し得ないが(民法177条、最判昭和33年8月28日民集12巻12号1936頁)、第三者の登記後に、占有者がなお引き続き時効取得に要する期間占有を継続したときは、占有者は、第三者に対し、登記なしに時効取得を対抗し得るところ(最判昭和36年7月20日民集15巻7号1903頁)、Xは、乙抵当権の設定登記の日から更に10年間占有を継続したのであるから、再度の取得時効が完成し、Yに対し、登記なしに、甲抵当権の制限のない完全な所有権の取得時効を対抗することができる」旨主張し、また、Bに対して取得時効を援用する旨の意思表示をした。 |
|---|
| 判旨 | 不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において、上記不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き取得時効に必要な期間占有を継続し、その期間の経過後に取得時効を援用したときは、上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、上記占有者が上記不動産を時効取得する結果、上記抵当権を消滅する(古川佑紀裁判官の補足意見あり)。 |
|---|
| 見解 | 1 本判決は、取得時効と登記についての判例の準則(*)を前提に、最判昭和36年7月20日民集15巻7号1903頁のように第三者が所有権の譲渡を受けてその旨の登記を得た場合と、第三者が抵当権設定を受けてその旨の登記を同様に解して、占有者が抵当権の存在を容認していたなどの特段の事情がない限り、抵当権設定登記時を起算点とする再度の時効取得を認めるとともに、時効取得は原始取得であることから、その反射として当該不動産に設定されていた抵当権が当然に消滅することを認めたものと理解される。 本判決では、抵当権に内在する換価力を前提に、所有権の時効取得者と抵当権者の間の権利の対立関係があることが上記判断の理由に挙げられていることからすると、地上権や賃借権等が設定された場合に本判決の趣旨が及ぶとは考え難い。 *取得時効と登記についての判例の準則 ⑴ 時効による所有権の取得は、時効完成の時期において所有者であった者に対しては登記なしにこれを主張することができる(大判大正7年3月2日民録24巻423号等)。時効完成前に原所有者から所有権を譲り受けた者に対しても同様に登記なしに時効による取得を対抗できる(最判昭和41年11月22日民集20巻9号1901号)。 ⑵ 時効完成後の第三者との関係は登記の先後によって優劣が決せられる(大判大正14年7月8日民集4巻412号)。 この場合に、時効取得者は、取得時効に必要となる占有期間の起算点を後の時期にずらして時効の完成を主張することはできない(最判昭和35年7月27日民集14巻10号1871頁)。 しかし、第三者の登記後にさらに取得時効に必要となる期間の占有を継続した場合には、第三者の登記時を起算点とする取得時効が完成する(最判昭和36年7月20日民集15巻7号1903頁)。 2 本件のように不動産に複数の抵当権が設定された場合には再度の取得時効の起算点をどの時点とするかが問題となるが、最初の権利の対立関係が生じた時点が起算点になると考えられることや、既に消滅した抵当権との間では権利の対立関係は解消していることから、再度の取得時効の起算点は、現存する最先順位の抵当権の設定登記時になると考えられる。 原告(被上告人)は、再度の取得時効の起算点として乙抵当権の登記設定時を主張したが、判決は上記の考えから甲抵当権の設定登記時を再度の時効取得の起算点とした。 3 本判決では、抵当権の保護の観点から、抵当権設定登記時を起算点とする再度の時効取得成立の除外事由として、「占有者が抵当権の存在を容認していたなどの特段の事情がある場合」を挙げているが、どのような場合に占有者が抵当権の存在を容認していたと認められるか等の点については、今後の事例の積み重ねを要するところであり、この点に関連して、抵当権者に抵当権の消滅を防止するためにどのような手段を講じる余地があるか等についても今後の議論の深化が期待される。 |
|---|
| 備考 | 抵当権者が占有者に対して執り得る手段としては、①原所有者が有する所有権に基づく明渡請求権を代位行使する方法(最判平成11年11月24日民集53巻8号1899頁参照)、②抵当権に基づく妨害排除請求権を行使する方法(最判平成17年3月10日民集59巻2号356頁参照)、③抵当権者が占有者に対して抵当権の存在を確認する旨の確認訴訟を提起する方法、④抵当権者の物権的請求権として、占有者に対して抵当権の存在を容認する旨の意思表示を求める方法等が考えられるが、いずれも理論的な問題や実効性に関する問題がある。 他方、一般には、抵当権者に対して、抵当権設定時に目的不動産の現況等を調査することを期待しても過度な負担を課すものとは言い難いことからすると、そもそも抵当権者に対抗手段を認める必要はないとの見解もある。 今後の検討課題である。 |
|---|
このページをご覧の方はこんな情報を閲覧されています。